<上がるときの25℃、下がるときの25℃>

床暖房の快適性、方式による比較など、床暖房についての情報は、さまざまなサイトで発信されているので、私は38年の経験から、少々はみだした話をしたいと思います。
今回は 上がるときの25℃と、下がるときの25℃の話です。
よくお客様から、床暖房をすると「何℃になるのか?」 「何℃が快適なのか?」 「どのくらいの時間で何℃まで上がるのか?」 と、”何℃” ということがよく言われます。
私は、新築建物が完成したときや、メンテナンスに伺ったときなど、よく温度計で計りながら様子をみます。
床暖房は温度の変化がかなり緩やかなので、計測器の数値がなかなか変わりません。
ところが、床面が加温状態で25℃を示している時と、加温をやめて、目に見えず冷めていく時の25℃はかなり異なるのです。
ズバリ 加温の25℃は”暖かく”、冷めるときの25℃は”寒く”感じられるのです。
おもしろいですよ。
<温水床暖房と電気床暖房>

つづいて、床暖房のはみだした話です。
私が目からウロコ!を感じた出来事です。
この仕事にとびこんだのは25才(1975年=昭和50年)です。少し脱線しますが、広島カープが初優勝した年です。
よく話に付き合ってくれていた 設備設計のHさんが、
「鈴木さん、温水床暖房と電気床暖房は暖め方が違うんだよね・・」といいました。
温水式は温度が一定で、ボイラーなら70℃程度、ヒートポンプなら50℃程度、---どんな状況でもそれ以上には上がりません。放熱量は暖める相手との温度差で
時々刻々 変化します。
電気式は放熱量が一定で、条件によって温度が変化します。
私はハッとしました。この仕事を続ける中で一番の"衝撃"でした。 温水床暖房と電気床暖房を比較したとき、上記の性質によって、良い点・違う点がそれぞれあるのです。
温度差が大きいときは、温水式床暖房の方が早く、温度差が小さいときは電気式床暖房が早いのです。
おもしろいですよ。
<床暖房のよび方>

私がこの仕事をはじめたのは38年位前、昭和50年(1975年)からですが、はじめたころ、”床暖房”の読み方も半信半疑でした。
「ゆかだんぼう」と読むのかな、「とこだんぼう」と読むのかな、と、真剣に悩んだこともありました。
床暖房、フロアヒーティング、床面加温、パネルヒーティング、・・と、似たような呼び方があります。
40年前頃は『パネルヒーティング』という呼び方が主流でした。
そのココロは、コンクリート層・石など、熱容量の大きいもの(=熱をたくさん貯められるもの、=暖まるのに時間がかかり、冷めにくいもの)に熱を蓄え、その表面から輻射熱を放熱する方法を指していました。
最近、『パネルヒーティング』というと、温水式にしろ、電気式にしろ、”ついたて”の形をしたパネルヒーターによる暖房を指すように思われますが、当時は違っていたのです。
ついたて形のものは、昔から「パネルヒーター」と呼ばれることが多かったのですが、「パネルヒーター」による暖房を『パネルヒーティング』とは呼んでいなかったのです。
不思議ですね。
特に空調(空気調和)の業界用語・学術用語としては、” 輻射暖房=放射熱暖房=パネルヒーティング ” でした。
私がはじめた頃に、「フロアヒーター(現在よく言われるパネルタイプ)」が登場してきて、床暖房が急速に普及しだしたのです。このフロアヒーターは、「パネルヒーター」とは呼ばれません。
ややこしいですね。
おもしろいですね。
<電気式と温水式のちがい――もっとはみだした話>

話がもっとはみだしますが、床暖房をはじめた頃は電気式が先行していました。
電気式のパネルタイプでない、埋設タイプの場合は、制御盤を作って制御することが多かったのです。
他の世界からとびこんだ私は、制御回路がなかなか理解できなくて苦労したものです。
その中に”接点”の話があります。
a接点 = 動作させようとする時「入る」もの
(日常に置きかえると、スイッチを入れると照明が点く、などです。)
b接点 = 動作させようとする時「切れる」もの
(日常に置きかえると、対震装置=地震があると切ってしまう。)
c接点 = 上記2つの動作が1組になって連動するもの
さて、電気の a接点のことを別の角度から見ると、・・・
「常時開」とか 「ノーマルオープン」とか 「NO」(=ノーマルオープンの頭文字)とか呼びます。
床暖房では、a接点によって動かします。「常時開」「ノーマルオープン」「NO」なので、スイッチを「入れる」動作によって働きます。ここまでは電気式の話。
さて、温水式になりますと、水道の蛇口を考えて下さい。蛇口を「あける」と水が流れて、「しめる」と流れが止まります。温水式では、「ノーマルオープン」は、「流れる」状態なのです。
話をまとめますと、電気と温水は逆なんです。電気式は「ノーマルオープン」から「クローズ」すると働いて、
温水式は「ノーマルクローズ」から「オープン」すると働くのです。
おもしろいですね。
<床面加温と床暖房>

実は,「床暖房」「フロアヒーティング」というのは、”玉虫色”の表現なのです。
<床暖房のよび方>の項も参照しながら読んで下さい。
輻射暖房=放射熱暖房=パネルヒーティングも、パネルタイプのフロアヒーターの働きも、”床面加温” という意味では同じように見えますよね。
ところがわかり易い例で考えてみますと・・・、
融雪・ロードヒーティングです。ほとんど似た素材を同じように働かせますが、輻射暖房ではありませんね。あくまで、床面加温(屋外ですから埋設面加温?)です。
室内でも、プールサイドや浴室の洗い場等も床面加温です。プール室全体の中で、プールサイドの面積はごくわずかです。輻射面(輻射パネル)で人間に対してパネルヒーティングを行うと言うのは無理がありますよね。
さらに、次の例として台所の流しの床などにパネルタイプを 一枚組み込んだ場合を考えましょう。
”足暖器”(そくだんき)と呼んだほうが適当のように思えますよね。
| 床面加温(埋設面加温)→ | ・パネルヒーティング(輻射暖房) ・融雪やプールサイド等の せまい意味の床面加温 ・局所的な床面加温、 いわば足暖器 |
これらを、ひとまとめに 「床暖房」 「フロアヒーティング」 という呼び方。
最初に命名した人はすごいと思います。
床暖房 フロアヒーティング、と聞くだけで温もりを感じます。
<床暖房は ”イキチ” をのむ!?>

床暖房(=輻射暖房としての床暖房)は立ち上がりに時間がかかります。
<床暖房のよび方>も参照して下さい。
その立ち上がりは、
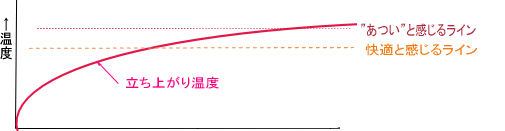 →時間 |
試運転などをしていると特に感じるのですが、わかっていても 「早く立ち上がらないかな」とイライラすることがあります。
しかし、適切な能力で働かせるといつかは快適ラインに達します。
ある一瞬「あ、立ち上がったな」と感じます。そしてその後は「暖かいな」、またしばらくすると「あついな」と感じます。
その感じ方が変わる値を 「閾値」(=イキチ)と言いますよね。
でも話し言葉で 「イキチに達したね」と言っていると、通りかかった人が一瞬「えっ!」とした顔をして通って行きます。文字で書くと何ともないんですが・・・・・。
ですから話し言葉のときは、あえて 「閾値」(=シキイチ)と言って区別しています。
( 「化学」を話し言葉では「バケガク」と言ったり、「市立(シリツ)○○高校」を 市立=「イチリツ」と言ったりしますよね。)
さて、その閾値は前掲のように カーブが相当 横になった所にあります。
何が関係してくるかというと、温度調節する際に、最後の(イキチに達する)0.5℃、1℃が ランニングコスト に大きく影響するのです。
カーブを見ていただくとわかっていただけますよね。
床暖房としては、快適に感じるギリギリのイキチで運転してもらいたいものです。